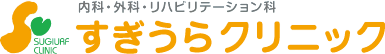胃潰瘍・十二指腸潰瘍とは
胃潰瘍・十二指腸潰瘍とは、胃や十二指腸の粘膜が炎症や血流障害によって傷つき、深くえぐれた状態になる病気です。潰瘍ができると、胃酸や消化酵素の影響で粘膜がさらに傷つき、痛みや出血を引き起こすことがあります。
胃潰瘍は主に食後に痛みが強くなるのに対し、十二指腸潰瘍では空腹時や夜間に痛みが強くなることが多いのが特徴です。どちらもピロリ菌感染やストレス、痛み止めの長期使用などが原因とされ、放置すると出血や穿孔(胃や十二指腸の壁に穴があくこと)といった重大な合併症を引き起こす可能性もあります。
早期に正確な診断を受け、適切な治療を行うことで、多くの場合は完治が可能です。胃の痛みや不快感が続くときは、早めの受診をおすすめします。
胃潰瘍は主に食後に痛みが強くなるのに対し、十二指腸潰瘍では空腹時や夜間に痛みが強くなることが多いのが特徴です。どちらもピロリ菌感染やストレス、痛み止めの長期使用などが原因とされ、放置すると出血や穿孔(胃や十二指腸の壁に穴があくこと)といった重大な合併症を引き起こす可能性もあります。
早期に正確な診断を受け、適切な治療を行うことで、多くの場合は完治が可能です。胃の痛みや不快感が続くときは、早めの受診をおすすめします。
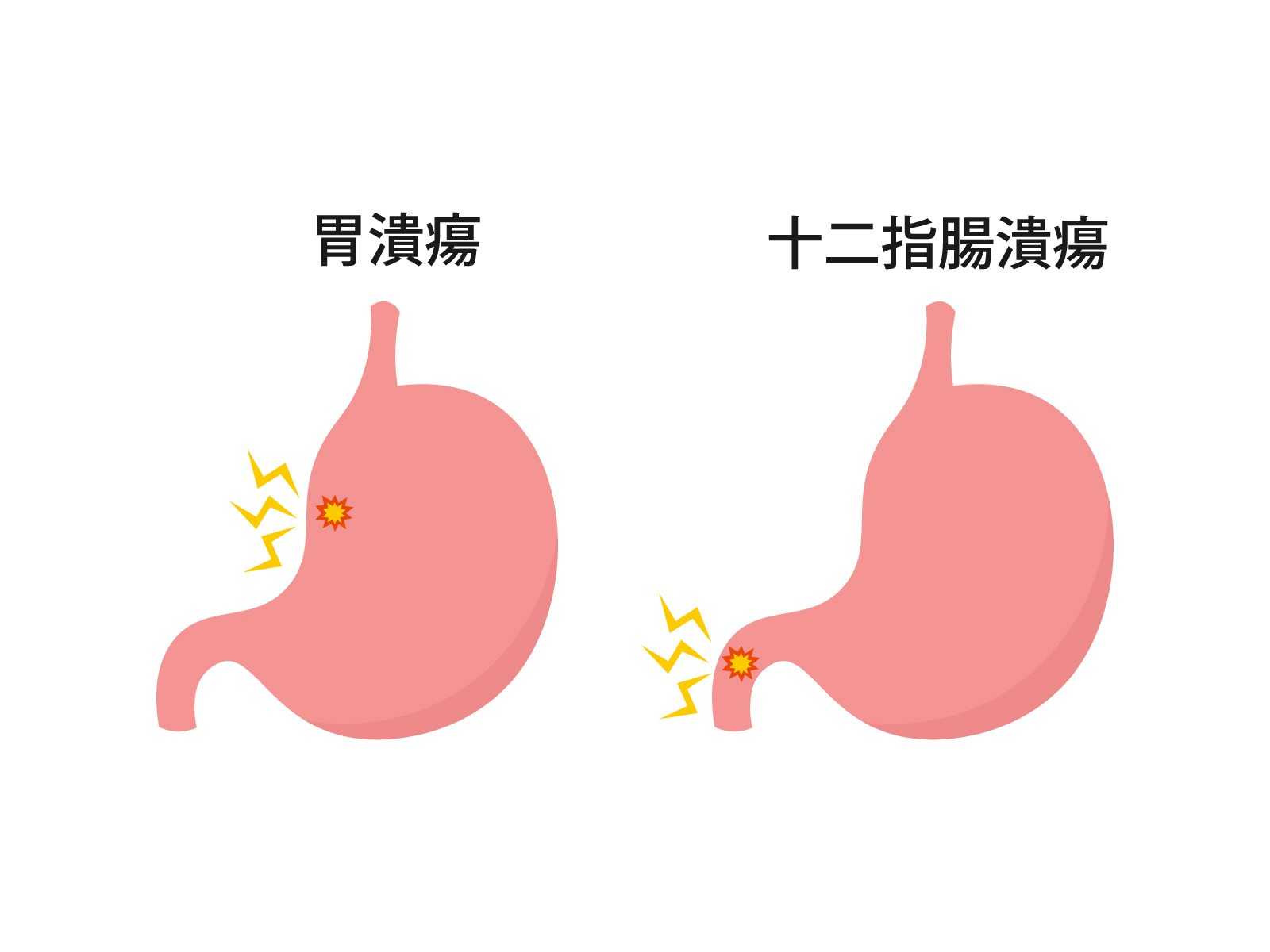

どんな症状が出る?見逃してはいけないサイン
胃潰瘍・十二指腸潰瘍では、次のような症状が現れることがあります。初期の段階では軽い不快感程度でも、放置することで深刻な状態に進行することがあります。
【主な自覚症状】
- みぞおち周辺の痛み
- 胃もたれや胸やけ
- げっぷや吐き気
- 食欲低下や体重減少
【注意すべきサイン(重症化の可能性あり)】
- 貧血症状(めまい・息切れ・倦怠感)
- 吐血:潰瘍からの出血が進行している場合
- 黒色便(タール便):胃や十二指腸からの出血の可能性
- 突然の激しい腹痛:穿孔(胃や十二指腸の壁に穴が開くこと)の可能性あり

原因はピロリ菌だけじゃない?主な原因とその背景
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因と聞くと「ピロリ菌」と思われがちですが、実際には複数の要因が関与しています。感染だけでなく、薬の副作用やストレス、生活習慣の乱れなども、粘膜を傷つける原因になります。ここでは主な3つの原因について解説します。
ピロリ菌
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)とは、胃の粘膜に生息する細菌で、強い胃酸の中でも生き延びることができます。感染すると、胃や十二指腸の粘膜に炎症を引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんのリスクを高めることが知られています。
主な感染経路は、幼少期における家族内での感染です。例えば、食器の共有や口移しによる食事などが原因となることがあります。また、発展途上国では不衛生な水や食べ物から感染するケースもあります。
痛み止めやストレスとの関係
市販の痛み止め(NSAIDs)を空腹時や長期間服用すると、胃や腸の粘膜が傷つきやすくなり、潰瘍の原因になります。特に高齢者や持病のある方は注意が必要です。また、強いストレスや過労、不眠なども粘膜の血流を低下させ、潰瘍を引き起こす要因になります。
悪化を招く生活習慣
喫煙は胃粘膜の血流を低下させ、潰瘍の治りを遅らせます。過度の飲酒はアルコールが胃壁を直接刺激し、炎症を引き起こす原因に。辛い物や熱い飲食物、脂っこい食事の摂りすぎ、早食いや深夜の食事、不規則な生活も胃に負担をかけます。ピロリ菌がいなくても、こうした生活習慣が原因で潰瘍になることはあり、再発防止のためにも生活を見直すことが大切です。

どうやって検査する?診断の流れ
胃カメラ検査の流れと準備
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の診断には、内視鏡検査(胃カメラ)が最も信頼性の高い方法です。医師がカメラを通して直接、胃や腸の粘膜の状態を確認し、必要に応じて組織の一部を採取して詳しい検査(生検)も行います。
経口内視鏡(口から挿入):一般的な方法。視野が広く、より詳細な観察が可能
経鼻内視鏡(鼻から挿入):嘔吐反射が少なく、会話しながら検査できる
当院では苦痛の少ない経鼻内視鏡を用いて検査しています。初めての方でも比較的楽に検査を受けていただけます。
・検査前日の夕食は軽めにし、21時までに食べ終わるようにしてください。
・検査当日は水・お茶以外の飲食は控えてください。
・毎朝飲まれている薬やサプリメントなどがある場合は指示に従ってください。
・血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を飲んでいる場合は、事前に申告してください。
■検査の種類
経口内視鏡(口から挿入):一般的な方法。視野が広く、より詳細な観察が可能
経鼻内視鏡(鼻から挿入):嘔吐反射が少なく、会話しながら検査できる
当院では苦痛の少ない経鼻内視鏡を用いて検査しています。初めての方でも比較的楽に検査を受けていただけます。
■検査当日の準備
・検査前日の夕食は軽めにし、21時までに食べ終わるようにしてください。
・検査当日は水・お茶以外の飲食は控えてください。
・毎朝飲まれている薬やサプリメントなどがある場合は指示に従ってください。
・血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を飲んでいる場合は、事前に申告してください。
ピロリ菌の検査(呼気・血液・便)
ピロリ菌の有無を調べる検査は、非侵襲的で体への負担が少なく、外来でも短時間で可能です。
尿素呼気試験(UBT):呼気を使って菌の有無を測定する検査です。当院では主に除菌判定の時に行っています。
ウレアーゼテスト:胃内視鏡検査の際に、胃粘膜の一部を採取して調べる検査です。
血液検査:ピロリ菌に対する抗体の有無を調べる検査です。過去の感染の有無も検出される可能性があるので、除菌判定には用いません。
便中抗原検査:便に含まれるピロリ菌抗原を検便で調べます。
■主な検査方法
尿素呼気試験(UBT):呼気を使って菌の有無を測定する検査です。当院では主に除菌判定の時に行っています。
ウレアーゼテスト:胃内視鏡検査の際に、胃粘膜の一部を採取して調べる検査です。
血液検査:ピロリ菌に対する抗体の有無を調べる検査です。過去の感染の有無も検出される可能性があるので、除菌判定には用いません。
便中抗原検査:便に含まれるピロリ菌抗原を検便で調べます。

潰瘍の治療法とその効果
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の治療は、原因に応じた内服薬の使用が基本です。多くの場合、適切な薬を一定期間服用することで症状は改善し、潰瘍も自然に治癒します。さらに、ピロリ菌が原因である場合には除菌治療が必要となり、再発防止にもつながります。 治療と同時に、生活習慣を見直すことも大切です。ここでは、代表的な治療法と注意点について詳しくご紹介します。
内服薬
潰瘍の治療で最も中心となるのが**胃酸の分泌を抑える薬(胃酸抑制薬)**です。胃酸の量を減らすことで、潰瘍部分の粘膜を保護し、自然治癒を促進します。
通常は数週間〜2か月程度の服用で改善が見られますが、症状や再発リスクによっては長期服用が必要なこともあります。
ピロリ菌除菌の流れと注意点
ピロリ菌に感染していると診断された場合は、胃酸を抑える薬と2種類の抗生物質を1週間服用する「除菌治療」を行います。治療後約2か月で呼気検査を行い、除菌成功を確認します。副作用として下痢や味覚異常が出ることがありますが、内服を終了すると自然に改善します。除菌薬を飲み忘れずに続けることが重要です。1回(1次除菌)で除菌できない場合は内服薬の内容を変えて再治療(2次除菌)を行います。2次除菌までは保険適用の対象です。除菌成功により潰瘍の再発リスクは大きく下がります。
治療中の生活で気をつけること
薬をしっかり飲むことに加えて、日常生活の中で胃腸に負担をかけない生活習慣を心がけることも重要です。
食事の見直し:刺激物(辛いもの・酸味の強いもの・熱い飲食物)を控える
規則正しい食生活:1日3食、よく噛んでゆっくり食べる
禁煙・節酒:喫煙は治癒を妨げ、飲酒は粘膜に負担をかける
ストレス管理:十分な睡眠・適度な運動・休息を意識
また、自己判断で薬をやめたり市販薬を追加で使用したりするのは避けましょう。気になる症状がある場合は、医師に相談することが大切です。
【治療中に気をつけたいこと】
食事の見直し:刺激物(辛いもの・酸味の強いもの・熱い飲食物)を控える
規則正しい食生活:1日3食、よく噛んでゆっくり食べる
禁煙・節酒:喫煙は治癒を妨げ、飲酒は粘膜に負担をかける
ストレス管理:十分な睡眠・適度な運動・休息を意識
また、自己判断で薬をやめたり市販薬を追加で使用したりするのは避けましょう。気になる症状がある場合は、医師に相談することが大切です。

当院でのサポート体制
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、早期発見と的確な治療が重要です。当院では、患者様一人ひとりの症状やご不安に寄り添いながら、検査から治療、再発予防までをしっかりサポートいたします。
「胃カメラは苦しい」という印象をお持ちの方も多いですが、当院では鼻から挿入する経鼻内視鏡を主におこなっております。
経鼻内視鏡は、喉の奥に触れにくいため嘔吐反射が少なく、検査中でも会話もできるという特徴があるので、検査中のモニターを見て説明しながら検査させていただきます。
「最近、胃の不調が気になる」「ピロリ菌の検査をしたい」といったご相談も、お気軽にご連絡ください。
当院では予約フォーム・お電話のどちらでも受け付けております。