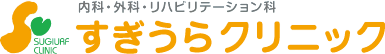こんな症状はありませんか?
次のうち、ひとつでも当てはまる場合は逆流性食道炎が疑われます。まずは原因を確認しましょう。
- 胸やけ:胸のあたりが焼ける・熱い感じがする
- 呑酸:酸っぱい液や苦い液が口まで上がってくる
- のどの違和感・声がれ:イガイガする、声が枯れる、長引く咳がある
- 体勢で悪化:前かがみ・重い物を持つ・ベルトを締めると悪化する
- 夜間・就寝中に増える:横になると症状が強く、枕を高くすると少し楽
- その他のサイン:ゲップが増える、口臭が気になる、胃もたれ・膨満感が続く
症状が続く・くり返す場合、経鼻の胃カメラで食道の状態を“見て”確認すると、治療の近道になります。

逆流性食道炎(GERD)とは?
用語の整理
GERD(胃食道逆流症)は、胃の内容物が食道へ逆流し、胸やけ・呑酸(酸っぱい液が上がる)・のどの違和感などを起こす状態の総称です。
このうち、内視鏡で食道の表面に炎症(びらん)が確認できるタイプを一般に「逆流性食道炎」と呼びます。
一方、症状はあるのに内視鏡でびらんが見えないタイプが非びらん性GERD(NERD)です。NERDでも日常生活に支障が出ることがあり、治療や生活改善が必要になる場合があります。
症状だけではびらんの有無を見分けられないため、必要に応じて胃カメラ(経鼻内視鏡)で可視化して方針を決めます。
なりやすい人・主な原因
食道と胃の境目にある下部食道括約筋(LES)がゆるみやすい体質・加齢、食べ過ぎや就寝前の飲食、肥満や前かがみ姿勢などで腹圧が高い状態は、逆流を起こしやすくします。
また、アルコール・炭酸・カフェイン・喫煙などの嗜好品、一部のお薬(種類によっては括約筋をゆるめたり胃の中に長く残りやすくするもの)も関係します。
横隔膜のすき間に胃の一部が入り込む食道裂孔ヘルニアがあると、逆流はさらに起こりやすくなります。
思い当たる原因がない場合でも、症状が続く・くり返すときは背景を確かめましょう。当院では必要に応じて経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、原因に合わせた対策をご提案します。

受診の目安
まず相談してほしいサイン
次のような場合は、症状の原因をきちんと確かめるために一度ご相談ください。
☑胸やけ・呑酸が週2回以上起こる/同じ症状をくり返す
☑睡眠や仕事・家事に支障が出ている(眠れない、集中できない など)
☑市販薬で十分に良くならない、やめるとすぐ再発する
☑夜間・就寝中に悪化する、前かがみや重い物を持つと強くなる
当院では、問診と必要に応じて経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、あなたに合った治し方をご提案します。
☑胸やけ・呑酸が週2回以上起こる/同じ症状をくり返す
☑睡眠や仕事・家事に支障が出ている(眠れない、集中できない など)
☑市販薬で十分に良くならない、やめるとすぐ再発する
☑夜間・就寝中に悪化する、前かがみや重い物を持つと強くなる
当院では、問診と必要に応じて経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、あなたに合った治し方をご提案します。
早めの受診が必要なサイン
次のサインがある場合は、早めの受診をおすすめします。原因を見て確かめ、必要な処置・検査にすぐ進みます。
☑食べ物がつかえる/飲み込みにくい
☑体重が意図せず減っている、食欲が落ちている
☑黒色便が出る、吐血が疑われる
☑強い胸痛、胸の圧迫感が続く・増えている
注意書き:強い胸痛は循環器疾患の可能性も。当院へまずご相談ください。
お急ぎの際はお電話でお問い合わせいただくと、受診の流れをご案内しやすくなります。
☑食べ物がつかえる/飲み込みにくい
☑体重が意図せず減っている、食欲が落ちている
☑黒色便が出る、吐血が疑われる
☑強い胸痛、胸の圧迫感が続く・増えている
注意書き:強い胸痛は循環器疾患の可能性も。当院へまずご相談ください。
お急ぎの際はお電話でお問い合わせいただくと、受診の流れをご案内しやすくなります。

当院で行う検査と診断
問診・診察で症状の型を見極めます
まず、症状が出るタイミング(食後・就寝前・前かがみなど)や頻度、悪化させる要因、既往歴・内服中のお薬を丁寧にうかがいます。胸やけ型なのか、のどの違和感や咳が前面に出るタイプなのかを整理し、心臓・呼吸器など他の病気が隠れていないかも確認します。そのうえで、胃カメラが必要かどうかを一緒に判断します。
必要に応じた胃カメラ検査
当院では経鼻胃カメラを扱っているため、口からの検査より「オエッ」となりにくいのが特長です。検査は短時間で、撮影した画像をその場でお見せしながら分かりやすくご説明します。
内視鏡以外の評価の考え方
症状の出方や生活との関係、内服への反応を手がかりに、方針を組み立てます。内視鏡で大きな異常が見つからない場合でも、食道の動きの問題や心臓・耳鼻科領域の病気が背景にないかをていねいに見きわめ、必要に応じて連携します。長く続く・くり返す症状は、胃カメラで食道の様子を直接確認すると安心につながります。

治療方針
生活習慣の見直し
まずは毎日の過ごし方を整えることが近道です。
☑就寝前2~3時間は飲食を控える/食後すぐ横にならない
☑腹八分目・ゆっくりよく噛む
☑枕やベッド上部を少し高くして眠る・左向き寝を試す
☑腹圧を上げない:きついベルトやガードルは避ける、重い荷物の持ち上げに注意
☑脂っこい料理・アルコール・炭酸・カフェインは量とタイミングを調整
☑体重管理・禁煙も有効です
当院では、症状の出方に合わせて実行しやすいコツを一緒に整理します。
☑就寝前2~3時間は飲食を控える/食後すぐ横にならない
☑腹八分目・ゆっくりよく噛む
☑枕やベッド上部を少し高くして眠る・左向き寝を試す
☑腹圧を上げない:きついベルトやガードルは避ける、重い荷物の持ち上げに注意
☑脂っこい料理・アルコール・炭酸・カフェインは量とタイミングを調整
☑体重管理・禁煙も有効です
当院では、症状の出方に合わせて実行しやすいコツを一緒に整理します。
薬物療法の基本
胃酸の分泌を抑える薬や粘膜を守る薬を、症状や内視鏡検査の結果に合わせて使い分けます。
☑飲み方のコツを明確にご案内
☑まずは短期間でしっかり症状を抑える→落ち着いたら量や回数を調整
☑生活の整え方と併用して再発しにくい状態を目指します
気になる副作用や相互作用は事前に説明し、無理のない計画で進めます。
☑まずは短期間でしっかり症状を抑える→落ち着いたら量や回数を調整
☑生活の整え方と併用して再発しにくい状態を目指します
気になる副作用や相互作用は事前に説明し、無理のない計画で進めます。
難治例への対応
症状が続く・戻りやすい場合は、
☑服用タイミングや量が合っているかを見直す
☑生活の工夫をもう一度具体化する
☑必要に応じて内視鏡でもう一度食道の様子を直接確認し、見落としがないかを確かめる
☑他の原因(食道の動きの問題、心臓・耳鼻科領域 など)が隠れていないか丁寧に見直す
上記の順で進めます。必要があれば専門機関とも連携し、過不足のない治療につなげます。困ったときは遠慮なく当院へご相談ください。
☑服用タイミングや量が合っているかを見直す
☑生活の工夫をもう一度具体化する
☑必要に応じて内視鏡でもう一度食道の様子を直接確認し、見落としがないかを確かめる
☑他の原因(食道の動きの問題、心臓・耳鼻科領域 など)が隠れていないか丁寧に見直す
上記の順で進めます。必要があれば専門機関とも連携し、過不足のない治療につなげます。困ったときは遠慮なく当院へご相談ください。

早く楽になるためのコツ
食事タイミング・量・内容
☑夕食は就寝の2〜3時間前までに。食後すぐ横になると逆流が起きやすくなります。
☑腹八分目・ゆっくりよく噛む。一度にたくさん食べず、量を控えめに。
☑脂っこい料理・辛い料理・チョコ・ミント・柑橘・トマト・玉ねぎ・炭酸・アルコール・カフェインは、量とタイミングを調整。特に夜は控えめに。
☑がぶ飲みは避けて、温かめの飲み物を少しずつ。夜食・間食はできるだけ減らしましょう。
☑体重が気になる方は、少量を回数で。無理のない体重管理も逆流予防につながります。
生活を整えても胸やけや呑酸が続く・くり返す場合は、当院で経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、あなたに合う治療に進みましょう。
☑腹八分目・ゆっくりよく噛む。一度にたくさん食べず、量を控えめに。
☑脂っこい料理・辛い料理・チョコ・ミント・柑橘・トマト・玉ねぎ・炭酸・アルコール・カフェインは、量とタイミングを調整。特に夜は控えめに。
☑がぶ飲みは避けて、温かめの飲み物を少しずつ。夜食・間食はできるだけ減らしましょう。
☑体重が気になる方は、少量を回数で。無理のない体重管理も逆流予防につながります。
生活を整えても胸やけや呑酸が続く・くり返す場合は、当院で経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、あなたに合う治療に進みましょう。
姿勢と寝具
☑寝るときは上半身を少し高く(枕を重ねる・ベッドの頭側を10〜15cmほど上げる)。
☑左向きで寝ると楽になる方がいます(個人差あり)。
☑食後2〜3時間は前かがみ作業を避ける。ベルトを緩め、自然に背筋を伸ばす姿勢を意識しましょう。
☑デスクワークが多い方は、こまめに姿勢リセットを。
☑左向きで寝ると楽になる方がいます(個人差あり)。
☑食後2〜3時間は前かがみ作業を避ける。ベルトを緩め、自然に背筋を伸ばす姿勢を意識しましょう。
☑デスクワークが多い方は、こまめに姿勢リセットを。
日常生活で避けたいこと
☑きついベルト・ガードル・腹部を締め付ける服は控えめに。
☑重い荷物の持ち上げ・腹筋系の強い運動は、食後は特に避ける。持つときは体に近づけ、膝を使ってゆっくり。
☑喫煙は逆流を助長します。禁煙を検討しましょう。
☑睡眠不足・ストレスは症状を悪化させがち。生活リズムを整え、休息を確保しましょう。
☑服用中のお薬の中には、逆流を強めるものがあります。自己判断で中止せず、当院にご相談ください。
これらを実践しても不快感が続くときは、我慢せず当院へ。必要に応じて経鼻の胃カメラをご案内し、その場で原因を見きわめて最短ルートの治療につなげます。
☑重い荷物の持ち上げ・腹筋系の強い運動は、食後は特に避ける。持つときは体に近づけ、膝を使ってゆっくり。
☑喫煙は逆流を助長します。禁煙を検討しましょう。
☑睡眠不足・ストレスは症状を悪化させがち。生活リズムを整え、休息を確保しましょう。
☑服用中のお薬の中には、逆流を強めるものがあります。自己判断で中止せず、当院にご相談ください。
これらを実践しても不快感が続くときは、我慢せず当院へ。必要に応じて経鼻の胃カメラをご案内し、その場で原因を見きわめて最短ルートの治療につなげます。

逆流をくり返さないために
症状が落ち着いた後の“維持療法”の考え方
症状が楽になったあとも、逆流は生活リズムや食事の影響でぶり返しやすい状態です。再発を防ぐために、次のような進め方をおすすめします。
☑段階的に薬を減らす/間隔をあける:急に中止せず、体調に合わせて少しずつ。
☑必要時のみの内服(オンデマンド):きっかけが分かっている方は、症状が出そうな場面で上手に使う。
☑生活の“型”を固定化:就寝前の飲食回避・腹八分目・姿勢の工夫を習慣に。
当院では、前回の症状の出方と検査結果を踏まえて、無理のない維持の方法をご提案します。
☑段階的に薬を減らす/間隔をあける:急に中止せず、体調に合わせて少しずつ。
☑必要時のみの内服(オンデマンド):きっかけが分かっている方は、症状が出そうな場面で上手に使う。
☑生活の“型”を固定化:就寝前の飲食回避・腹八分目・姿勢の工夫を習慣に。
当院では、前回の症状の出方と検査結果を踏まえて、無理のない維持の方法をご提案します。
再燃サインを見逃さない
次のような変化は再燃のサインです。早めに内服や生活のコツを調整しましょう。
☑週2回以上の胸やけ・呑酸が戻る、夜間に目が覚めることが増えた
☑生活の変化(残業・飲み会・出張・引っ越し・季節の変わり目)で症状が不安定
☑前かがみ作業や運動後に悪化、市販薬で一時的にしか楽にならない
我慢せず、症状が軽いうちにご相談ください。必要に応じて経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、今の状態に合った治し方に切り替えます。
☑週2回以上の胸やけ・呑酸が戻る、夜間に目が覚めることが増えた
☑生活の変化(残業・飲み会・出張・引っ越し・季節の変わり目)で症状が不安定
☑前かがみ作業や運動後に悪化、市販薬で一時的にしか楽にならない
我慢せず、症状が軽いうちにご相談ください。必要に応じて経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、今の状態に合った治し方に切り替えます。

よくある質問
何科を受診すればよい?
胸やけ・呑酸・のどの違和感は内科・消化器内科で診られます。当院では問診と診察を行い、必要に応じて経鼻の胃カメラで食道の様子を直接確認し、その場で今後の進め方をご案内します。胸痛が強く不安な場合も、まず当院へご相談ください(必要時は適切な診療科とも連携します)。
市販薬で様子を見てもいい?
一時的に楽になることはありますが、くり返す・長引く・夜間に悪化する場合は、自己判断で内服を続けるより原因をきちんと確かめることが大切です。食道の炎症や狭くなる変化、別の病気が隠れていないかを確認し、あなたに合った治し方へ進みましょう。迷ったら早めに当院へ。
胃カメラはつらくない?経鼻と鎮静の違い
当院は経鼻内視鏡に対応しています。口からより**「オエッ」となりにくく**、会話もしやすいのが特長です。強い不安がある方には**鎮静(うとうとした状態)**での実施も可能。いずれも短時間で、画像をお見せしながら分かりやすくご説明します。準備や注意点は事前にスタッフが丁寧にお伝えします。
妊娠中・授乳中は?
妊娠週数や体調、症状の強さを踏まえて、実施の可否やタイミングを個別に決めます。実施が必要な場合は、安全面に配慮して方法を選びます。授乳中は、お薬や鎮静の有無に応じて授乳のタイミングを調整します。まずは遠慮なくご相談ください。
子どもでも起こる?
お子さまでも起こることがあります。年齢によって診かた・進め方が異なるため、まずは症状や生活の様子を丁寧にうかがい、無理のない方法をご提案します。必要に応じて小児科とも連携しますので、気になる症状があれば早めに当院へご相談ください。

苦痛の少ない胃カメラ検査をご検討の方へ
当院は経鼻内視鏡に対応しています。口から入れる方法に比べて嘔吐反射が起こりにくく、会話もしやすいため、はじめての方でも受けやすい検査です。検査時間は短く、撮影した画像を一緒に見ながらその場で分かりやすくご説明します。衛生管理を徹底し、安心して受けていただける環境を整えています。